寒いと思ったときは暖房器具の出番。あなたは何を使っていますか?
ズバリ、おすすめしたいものの一つに「電気あんか」があります!
暖房器具には、石油ファンヒーターや電気毛布、こたつなどいろいろな種類がありますよね。
私は部屋を暖めるために石油ファンヒーターを使っていたのですが、寝ている間はつけたままにできないうえに、冷たい布団もネックで悩んでいました。
布団が温かくなる何かいいものはないかな?と探していた中で見つけたのが電気あんか。
使い方のみならず、謎の多そうな電気あんかですが、実は、電気屋さんやAmazonなどのネットでも簡単に見つかり、しかも大人気なのです。
使い方も簡単でさらに電気代の安価なのです。
電気あんかを使いだしたらそのコスパの良さにやみつきです。
使い方・注意点などを徹底的に調べたのでご紹介します。
電気あんかの使い方はとても簡単!

電気あんかの使い方はとても簡単です。コンセントを繋ぐだけですぐに温くなります。
布団が冷たいと眠りに入りにくいだけではなく、なかなか温まらない。
寝ようと思っても寒くて寒くて体温調整がうまくできずなかなか寝付けずに、そのまま眠っても眠りが浅くなってしまいます。
電気あんかは、寝る前まで布団の中を温めるために使い、寝るときには電源を切るようにする使い方が理想です。
寝るときに布団の中が温かいと寝付きがよくなり、心地よい眠りに入ることができます。
寝る前には必ず電気あんかの電源を切ってから寝るようにしましょう。
温かい布団で寝られるとそれだけで幸せを感じるのは私だけでしょうか…!
そして、電気あんかが使えるのは、実は寝るときだけではないのです。
寝るとき以外にも電気あんかのおすすめの使い方があるので紹介します。
夜寝る前以外にも使える!電気あんかのおすすめの使い方
- 机の足元に置いて、膝掛けをかけて中を温めて使う
- こたつを付けるほどではないときにこたつに入れて使用する
部屋全体を暖めてしまうと眠たくなってしますよね。電気あんかは、足元だけを温かくできるので、受験生やデスクワークの方にはおすすめですなのです。
とても簡単に使えていい!…と一見メリットしかないのでは?と思ってしまいますが、実はデメリットも存在します。
とらえ方は人それぞれですが、一般的に考えられるメリットとデメリットについてまとめました。
電気あんかのメリットとデメリット

電気あんかは、名前の通り電気で温めて使う暖房器具。
使い方をマスターし、しっかりと使えば、コスパもよく、いいことづくしの暖房器具です。
しかしこの電気あんかの「使い方」を間違うと、少しやっかいです。
電気あんかの上記だけでないメリットと、デメリットをまとめてみました。
電気あんかのメリット
とくに電気代は他の暖房器具と比べても安価です。何よりもメリットですね。
| 温度:強 | 温度:中 | 温度:弱 | |
| 表面温度 | 約60度 | 約45度 | 約30度 |
| 1時間あたりの電気代 | 約0.2円 | 約0.1円 | 約0.05円 |
ちなみに、例えばエアコンは、1時間あたり約20円~。他、電気毛布や床暖房など、さまざまな暖房器具との比較についてこちらの記事でご紹介しています。

また、本体価格も2000円程度と比較的お安く手に入ります。
電気あんかのデメリット
電気あんかだけではないのですが、身体に触れる可能性があるものには低温やけどのリスクがあります。ホッカイロなどもよく注意書きがありますよね。
また、コンセントを抜くのは忘れがちになりますが、必ず抜きましょう。こちらも電気あんかに限った話ではありませんが、注意が必要です。
1つ1つ下記でご説明しています。
電気あんかで起こる低温やけどの危険とは!?

低温やけどは44℃〜50℃のものに長い間体が触れていると起こると言われています。
普通のやけどと同じ症状が出るのですが、自覚症状が少ないです。
そのため、やけどに気づくのも遅くなり、重症化してしまう場合があります。
低温やけどは、皮ふの深くまでやけどしていることが多く、治りにくく、悪化する恐れもあります。
低温やけどを防ぐためには、電気あんかは必ず体から離して使うように注意してください。
特に以下に当てはまる人は十分注意が必要です。「使用前に温める」使い方のみでの使用が望ましいでしょう。
低温やけどになるまでの時間は?
長い時間体に当たっていると低温やけどになると言いましたが、実際どのくらいの時間でやけどしてしまうのか気になりますよね。
| 皮ふの表面温度 | 低温やけどまでの時間 |
| 44℃ | 3〜4時間 |
| 46℃ | 30分〜1時間 |
| 50℃ | 2分〜3分 |
低温やけどになるまでの時間が意外と短くて驚きました。電気あんかの温度調整は「中」で表面温度が約45℃です。
30分以上同じ場所に当てていると低温やけどになる可能性があります。
電気あんかをつけっぱなしにして寝ると、低温やけどをするリスクが存在しますので避けましょう。
しかし寒い冬についつい体に当ててしまいたくなりますよね。低温やけどを防ぐ方法を調べてみました。
電気あんかで低温やけどを防ぐ方法
- 寝るときには電気あんかをつけっぱなしにしない
- 長い時間使いたいときは厚手のタオルにくるんで、温める場所を適度に変える
- タイマー付きの電気あんかを使う
ついつい触れていたくなりますが、寝るときは必ず電源を切りましょう。
私は寝相が悪く、電気あんかを体から離せない可能性があるので、寝る前まで温めてから温かくなった布団で寝るようにしています。
寝るとき以外で使用したいときは、万が一触れてしまってもいいように厚手のタオルにくるむと、リスクを減らすことができます。
電気あんかのつけっぱなしは火事の危険性がある

電気あんかをつけっぱなしにすると火事にならないのか、電化製品全般気になるとこですよね。
電化製品なので絶対火事にならないとは言えません。実際に電気あんかが原因の火事は起きています。
ほとんどの電気あんかは、何らかの原因で本体が熱くなりすぎると、安全装置が働き電源が切れるようになっています。
しかし電気あんか本体の問題ではなく、やっかいなのがコードです。
電源コード部分は、電化製品すべてに共通する、火事の原因となりうるもの。
コード部分の接触不良があると、そこが原因で火事になることが多いようですね。
電気あんかでも火事の危険性はありますので、安全な使い方が大切になってきます。
火事にならないために
- 電源コードを折り曲げない、引っ張らない
- 収納するとき、コードをあんか本体に巻かない
- 電源コードを束ねて使用しない
- 不具合が起こったらすぐに使うのをやめる
- 犬や猫に電源コードを傷つけられないように注意する
- 変形する可能性があるため、電気毛布と一緒に使わない
- 電源コードを家具で踏んだりドアで挟んだりしない
- コードを抜くときは根本を持って抜く
取扱説明書に詳しく書かれているのでご確認ください。
電源コードは電気あんかだけの話ではありません。また、電源コードはそんなに簡単には断線しませんが、劣化しているととても危険です。
使っていて、焦げたにおいがしたり、コードが少しでも傷んできたなと思ったら買い替えましょう。実際メーカーは交換期限を5〜6年と伝えています。
電気あんかと湯たんぽの違い

同じく布団を温めるのに大活躍する道具があります。それは湯たんぽ!
湯たんぽは、お湯を入れて暖める暖房器具ですね。湯たんぽを使おうとすると、お湯を沸かして、お湯を入れなくてはいけません。
電気あんかと湯たんぽの違いを、メリットとデメリットで同じく比較しています。
あたため効果が同じ湯たんぽのメリット
何よりもコンセントを使わないでいいのが最大の違いですよね。
もちろん、さきほど示した「火事の危険性」もありません。
あたため効果が同じ湯たんぽのデメリット
温度は一般的には下がっていくものなのでリスクは少ないのですが、湯たんぽも低温やけどのリスクがあるので要注意です。
そしてわずかですが、電気代がかかることは忘れがちです。
さらには電気あんかよりも湯たんぽの方が電気代が高くなる可能性があるのです。
| 湯たんぽ1回にかかる光熱費 | |
| 水1Lの水道代 | 約0.3円 |
| 1Lを沸騰させるガス代 | 約2.2円 |
| 1Lを沸騰させる電気代 | 約2.7円 |
湯たんぽは、使用する際には電気を使わないので電気代かからない!と思いがちですが、実はそれなりにかかっています。
布団を温めるのに大活躍する2つですが、それぞれにメリットデメリットがありますね。
電気あんかは平型以外もある!

最後に、電気あんかの種類についてご紹介します。
電気あんかには種類がたくさんありますが、型の違い、素材の違いなどをご紹介いたします。
※具体的なおすすめ品はこちらの記事へどうぞ♪

平型
電気あんかといえば平型を思い浮かべる人も多いぐらい、昔ながらのスタンダードな形です。
コンパクトで持ち運びも簡単なので、毛布やひざ掛けと一緒に使ってこたつの代わりとしても使えます。
山型と違い布団の中で使うと、適度な空間を作れないので、長いとき間使っていると蒸れる可能性があります。
山型
山型の電気あんかは、布団の中で使うことを想定されて作られています。布団の中に適度な空間が作られるので、電気あんかから足が離れても温かいです。
ソフトタイプ
とても柔らかい素材が使われています。大きいサイズと一般的なサイズのソフトタイプがあります。
大きいサイズは布団を温めるのに最適です。山型と違い温まる範囲が広いのもうれしいですね。
しかし、大きいサイズは一般的なサイズと比べると、本体価格が少し高くなります。ソフトタイプは温度調整ができないことが多いので、温度調整をしたい方にはおすすめできません。
蓄熱式
コードレスなのでコンセントがない場所でも使えますね。充電するのを忘れないようにしてください。いざ使おうと思っても使えません。
1回、15分〜20分の充電で6〜8時間使えるので、寝る前に使っても朝まで温かいです。
電気あんかの種類が多くて、自分が使う用途に合わせて選べるのは嬉しいですね。私はコードレスの蓄熱式だとどこでも使えて便利なので気になりました。
まとめ

- 電気あんかの使い方はコンセントに繋ぐだけ
- 電気あんかは寝る前に使って、寝るときには電源を切る
- エアコンやこたつと一緒に使うと良い
- 電気あんかは電源を入れるとすぐに温かくなる
- 電気あんかは長いとき間体に当てていると低温やけどのリスクがある
- 湯たんぽより電気あんかの方が光熱費は安い
- 電気あんか本体では火事になることはないが、コンセントや電源コードが原因で火事になる場合がある
電気あんかは使い方が簡単です。本体価格も電気代も安く、ピンポイントで温まるだけではなく、他の暖房器具と合わせて使うことができ、万能だとわかりました。
しかし、電気あんかの使い方を間違えると、低温やけどや火事になるリスクが高くなります。安全に正しく使って寒い冬を乗り切りましょう。
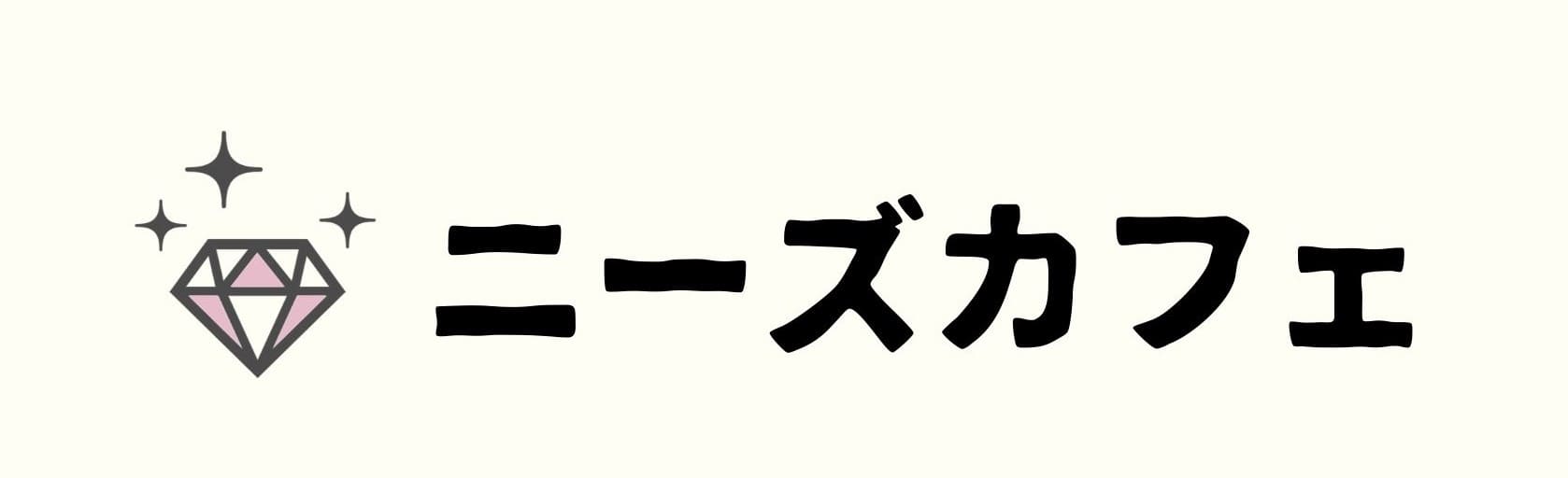



コメント